日本茶が私たちのもとに届くまでに、実にいくつもの工程があります。その中でも、「仕上げ茶」という工程が果たす役割をご存じでしょうか?
茶畑で摘み取られた茶葉は、蒸し・乾燥といった一次加工を経て「荒茶」と呼ばれる状態になります。しかし、このままでは、形状や品質にばらつきがあり、飲みやすいお茶とはいえません。そこで、選別・火入れ・整形などの仕上げ加工を施し、茶葉の品質を均一化して香りや味わいを引き出したものが「仕上げ茶」です。
本記事では、仕上げ茶の定義や加工工程を詳しく解説し、その重要性や魅力について掘り下げていきます。
仕上げ茶とは?

仕上げ茶とは、茶農家が生産した荒茶に対して、さらなる加工を施して商品化されたお茶のことを指します。
摘んだ茶葉をそのまま乾燥させずに水分を抜いたり、揉んだり、大きさを分けたりとさまざまな加工工程を経ることで、飲める状態になります。これらの各加工が行われることで、茶葉本来の深い香りや甘い味わいなどが引き出されるのです。
仕上げ茶と荒茶(あらちゃ)の違い
荒茶(あらちゃ)とは、仕上げ茶の前段階のお茶です。
摘んだ茶葉を放置しておくと、茶葉内に含まれる酸化酵素によって発酵が進んでしまいます。そこで、蒸熱(じょうねつ)とよばれる熱処理を施すことで、茶葉内の水分量が減って発酵が抑えられ、長期保存できるようになります。このお茶が荒茶です。
荒茶はあくまでも長期保存できるように処理をしただけであるため、茶葉の大きさや形状はバラバラです。茶葉のなかに茎や粉なども混ざっています。
もちろん荒茶の状態でも飲むことはできます。ただし、荒茶は流通量が少なくお店ではほとんど売られていません。
この荒茶に仕上げ加工を施したものが、今回ご紹介している仕上げ茶です。仕上げ茶は茶葉の大きさや形状が均一になり、茎や粉は取り除かれ、味や香りも整います。茶葉の色も荒茶と比べると深く美しい緑色になります。

仕上げ茶と煎茶の違い
煎茶とは、荒茶を一般流通できるように加工したお茶(緑茶)です。つまり、煎茶=仕上げ茶の1つであるといえます。
仕上げ茶の加工工程(仕上げ加工)

ここでは、荒茶が仕上げ茶になるまでの加工工程を解説します。ちなみに後述する分別と火入れは順序が逆になることもあります。先に火入れしてから分別するのは「先火方式」、分別してから火入れを行うのは「後火方式」とよばれます。
1:分別
前述のとおり、荒茶の段階ではまだ茶葉の大きさや形状は不均一で、茎や粉も混ざっています。仕上げ茶に加工する際は、まず荒茶を専用のふるいにかけます。その後、長さや太さなどで5段階ほどに分けていきます。
ちなみに、大きすぎる茶葉は頭茶(あたまちゃ)とよばれます。頭茶は小さく切断して茶葉のなかに戻されるか、別途分けてほうじ茶や番茶に使われます。
また、ふるいにかけることで茎や粉も分けられます。茎は茎茶(くきちゃ)に、粉は粉茶(こなちゃ)にして販売されます。

2:火入れ
火入れとは、コーヒーでいう焙煎(ロースト)と同じ工程です。分別した茶葉をそれぞれ加熱します。加熱方法は、茶葉に直接火を当てたり、熱風を当てたり、熱い鉄板の上で炒ったりなどさまざまな方法があります。
加熱されることで水分が抜け、茶葉本来の深い香りや味、美しい色合いなどが引き出されます。火入れでは、少しの温度や火加減で仕上がり方が大きく異なります。美味しい仕上げ茶にする重要な工程であるため、経験や技術をもった茶師が行います。

3:冷却
火入れした茶葉を自然冷却します。
4:合組(ブレンド)
合組とは、複数の茶葉をブレンドする工程です。茶葉はその年の品種の割合や気候などで味や香りが変わります。それぞれの特徴を鑑みながら合組(ブレンド)することで、1つの茶葉では出せない美味しさや香りが生まれます。
茶葉ごとの味や香りの特徴を把握し、適切なバランスで混ぜていく経験則が求められるため、豊富なお茶の知識や経験をもつ茶師が行うのが一般的です。

山年園で販売している仕上げ茶(煎茶)について
山年園でも、オリジナルの仕上げ茶(煎茶)を販売しています。
とげぬき地蔵茶は、渋みが強くしっかりした味わいで濃厚な煎茶が好きな方におすすめ。揖宿 頴娃(いぶすき えい)は、個性的な甘い香りとすっきりした後味が特徴です。やぶ北茶は、甘みと渋みのバランスが程良く、クセがなくて飲みやすい煎茶です。
とげぬき地蔵茶
| 商品名 | とげぬき地蔵茶 |
| 商品区分 | 飲料 |
| 内容量 | 【1袋あたりの内容量】 100gまたは200g |
| 原材料名 | 茶葉 |
| 原産地 | 日本[Made in Japan] 静岡県掛川市 |
| 使用上の注意 | 開封後はお早めに召し上がりください。 |
| 保存方法 | 常温保管してください。高温多湿、直射日光は避けて保管してください。 |
| 賞味期限 | 製造日より約12ヶ月 |
| 販売事業者名 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |
| 店長の一言 | 当店限定の巣鴨とげぬき地蔵茶です。 参拝茶と比べて、茎を抜いてあり、渋い味が特徴的です(^-^) |
煎茶 頴娃(いぶすき えい)
| 商品名 | 煎茶 頴娃 |
| 商品区分 | 飲料 |
| 内容量 | 【1袋あたりの内容量】 100g |
| 原材料名 | 茶葉 |
| 原産地 | 日本産 鹿児島県頴娃町 |
| 使用上の注意 | 開封後はお早めに召し上がりください。 |
| 保存方法 | 常温保管してください。高温多湿、直射日光は避けて保管してください。 |
| 賞味期限 | 製造日より約12ヶ月 |
| 販売事業者名 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |
| 店長の一言 | 甘い味で一躍大人気になった煎茶です。 甘い煎茶を飲みたい方にぴったりです(^-^) |
煎茶 やぶ北茶
| 商品名 | 煎茶 やぶ北茶 |
| 商品区分 | 飲料 |
| 内容量 | 【一袋あたり】100g(5g×20パック) |
| 原材料名 | 茶葉 |
| 原産地 | 静岡県 |
| 使用上の注意 | 開封後はお早めに召し上がりください。 |
| 保存方法 | 常温保管してください。高温多湿、直射日光は避けて保管してください。 |
| 賞味期限 | 製造日より約12ヶ月 |
| 販売事業者名 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |
| 店長の一言 | 老舗のお茶屋が販売する煎茶です。 他店のお茶と比べてみてください(^-^) |
最新記事 by 塩原大輝(しおばらたいき) (全て見る)
- ふきのとう味噌(蕗みそ/ばっけ味噌)の作り方や美味しいレシピを紹介! - 2025年3月30日
- かつお昆布(鰹昆布)のおすすめの使い方!アレンジレシピや作り方についても - 2025年3月27日
- 花削り昆布(花けずりこんぶ)のおすすめの使い方|うま味やミネラルたっぷり! - 2025年3月23日












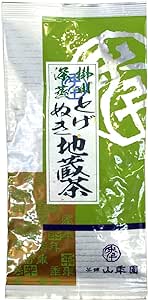
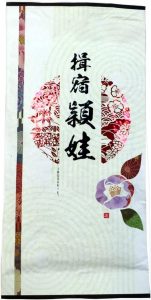
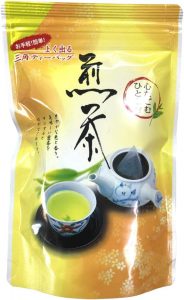


 山年園でお買い物
山年園でお買い物

